こんにちは、takamasaです。
この時期は卒業シーズンですね、中には来月から新社会人になる方もいらっしゃることでしょう。
そんで社会人になってからの大きな課題の一つとして、学生時代の過ごし方からの切り替えが挙げられるかと思います。(実は自分も会社員の頃に指摘されたことがあり、悩まされました。)
それを踏まえて、今回は学生を卒業して社会人を経験中の自分が学生と社会人の考え方の違いについて考えてみたいと思います。
時間を守る
学生でも社会人でも約束の時間を守らないと相手に迷惑がかかることは想像できるでしょう。
ですが、学生と社会人とでは迷惑の度合いが違います。
学生のうちは叱られるだけで済まされましたが、社会人となると信用を失うきっかけとなってしまい仕事ができなくなることがあります。
そうなると自分だけでなく自分の会社や団体にとって不利益となってしまいます。
たかが遅刻しただけと思いがちですが、時間を守れないということはタイムマネジメントができないつまり期限までに仕事をこなせない人とみなされてしまうことがあったりします(事故や危篤など予想外な出来事が起きたことを考えたら一概に言い切れないところはあると思いますが、、、)。
なので特別遅れる要因がなければ、時間は守った方が損はないでしょう。
感情に振り回されない
これは時々自分でも課題になりますが、感情に振り回されないということも必要な要素かもしれません。
子どもの頃は泣いたり怒ったりすれば周りの大人がなんとかしてくれる場面があったかもしれませんが、大人になればそうはいきません。
ましてや社会人となると周りからの仕事のやり辛さや幼稚な人として批判されたり相手にされなくなることでしょう。
ただ常日頃から感情を抑えろということではなく、仕事の時やフォーマルな場面(冠婚葬祭など)ではせめて感情を出しすぎないようにすることも成人として必要なことかもしれません。
考えを自分で生み出す
社会人から見て学生が楽に見える理由の一つとして、「問題に対して調べればすぐに答えが出るから」というのを聞いたことがあります。
確かに学生(特に卒論研究前の大学生まで)は問題に対して先生に聞いたり調べたりすれば何かしら答えが出てくることが多かったです。
卒論研究や社会人となると、ある程度進め方までは調べられても最終的な答えは調べても載ってないことが多いと感じます。
つまり、研究者や社会人にとって問題に対する答えは見つからない、逆を言えば答えを自分で作り出すことが求められるのではないかと思いました。
なので時々、自分で考え出すという習慣を学生のうちからつけておけば良かったと後悔することもあります、、、。
すぐに答えを求めるのではなく、まずは自分で仮の答えを出すこと。
今回の違いを考えてみて、まだまだ自分にも課題がいっぱいありそうだなと思った今日この頃でした。
今回は以上です、ここまで読んでいただきありがとうございました!また次回もお楽しみに!
前回の紹介記事:【一区切り】ほぼ毎日日記投稿を継続した感想と学び

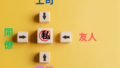

コメント